

7/3(土)に開幕する〈HOPE JAPAN 2021〉東京バレエ団全国ツアーでは、7年ぶりにモーリス・ベジャール振付「ギリシャの踊り」を上演します。
本作の上演にあたり、長年プリンシパルをつとめた吉岡美佳(現・東京バレエ団特別団員)が来団し、指導にあたっています。ベジャール作品を熟知する彼女に初演時の思い出や作品の魅力、リハーサルの手応えを語ってもらいました。ぜひご一読ください。

政本絵美(写真左・ハサピコ パ・ド・ドゥ)を指導する吉岡美佳(写真右)
──吉岡さんは2003年の東京バレエ団初演から『ギリシャの踊り』に出演されていましたね。当初、この作品にどんな印象を抱いていらっしゃいましたか。
吉岡美佳 『ギリシャの踊り』に初めて触れたのは、20世紀バレエ団のミシェル・ガスカールさんがソロを踊っている映像でした。とても手の長い素敵なダンサーですが、その踊りに引き込まれ、なんて素敵な作品なんだろうと心を奪われたものです。この作品は、ミキス・テオドラキスの音楽に"一目惚れ"したというベジャールさんが、ガスカールさんを中心に据えて振付けたバレエですが、ガスカールさんに最初にこの音楽を聴かせた時、二人で顔を合わせて無言でうなずき合ったと聞いています。
──吉岡さんが踊られていたパートは?
吉岡 『ギリシャの踊り』には男女のパ・ド・ドゥの場面が二つありますが、私は当初、6番目に登場するハサピコ──私たちはヴァルナと呼んでいる場面のパ・ド・ドゥに配役されていました。その後リハーサルにいらしたガスカールさんが、「ミカは"裸足のパ・ド・ドゥ"(ヴァルナの一つ前に出てくるパ・ド・ドゥ)が似合うのではないか」とおっしゃって、電話でベジャールさんの了承を得られたのです。それで急遽、初日は"裸足"、2日目にヴァルナを踊ることになりました。"裸足"は音楽も振付もとても可愛らしくて素敵で、キャスティングされる前からいいなと思っていたので、とても嬉しかった! それからずっと、『ギリシャの踊り』を上演するたびに、私は2つのパ・ド・ドゥを日替わりで踊っていました。

裸足のパ・ド・ドゥのリハーサルより、写真左から沖香菜子、秋山瑛、大塚卓
──対照的な雰囲気の二つのパ・ド・ドゥは、どちらも独特の魅力があります。
吉岡 "裸足"のパ・ド・ドゥは、可愛らしい、若い男女が戯れているような踊りです。対するヴァルナのパ・ド・ドゥの女性は、こう、つんとすましてタバコを燻らしているような大人の雰囲気。昨年上演した『M』でも、『ギリシャの踊り』とは性格が異なるけれど、白い衣裳の"海上の月"と黒い衣裳の"女"という対照的な二人の女性が登場します。ベジャールさんの作品にはこうして正反対のキャラクターの女性が出てくることが多いですね。
──幕が開いたその瞬間から、まるでギリシャの砂浜がそこに広がっているかのような感覚になります。
吉岡 例えば群舞のシーン──。地面に手をついて、ふっと離す場面があります。太陽の下の熱い砂浜に手をついたときのイメージです。それから、手を広げて天を仰ぐのは、太陽の光を全身で受け止めるような感じを想像して、と指導していただきました。ただしベジャールさんは、"ギリシャの踊り"だからといってギリシャ特有のパを羅列するようなことは決してしない。それに、その土地その土地の踊りといえば伝統的な衣裳を着るのが常だけれど、そういったものは一切なし、レオタードにタイツと、衣裳は極めてシンプルです。こうした簡素化によって、より音楽、踊りが際立つというわけなんです。男性たちの筋肉の美しさ、若々しさもぐんと際立ちます。男性同士のパ・ド・ドゥなんて、力強いだけでなく、粋というかお洒落というか、なんとも言えない雰囲気です!

ソロを踊る樋口祐輝(写真左)、柄本弾(写真右)
──あらためて、この作品の魅力はどんなところにあると思いますか。
吉岡 全員の群舞があって、娘たちの踊りがあって、男性同士のパ・ド・ドゥ、男性のソロ、2つの男女のパ・ド・ドゥ──と、いろんな踊りが登場し、それぞれに違った色を見せてくれる。東京バレエ団のダンサーたちの魅力を見ていただくのにぴったりの作品ではないでしょうか。ダンサーの配置やフォーメーションも本当に素晴らしく、そんなところにもベジャールさんの凄さを感じるのです。
ベジャールさんのバレエはどの作品もとても音楽的ですが、とりわけこの作品は、ベジャールさんがテオドラキスの音楽に惚れ込んで創作したものですから、ダンサーたちも音楽に身を委ね、パを正確に踊ることで、自然に作品の中に入り込んで、作品の一部になれると思うんです。
──全国ツアーに向けて、リハーサルは順調に進んでいるようですね。
吉岡 世代交代が進み、ベジャール作品の経験が少ないダンサーが大多数に。彼らにベジャール作品を伝える難しさを感じることもありますが、ガスカールさんに指導していただいたことをなるべく多く、皆に伝えたいと思って取り組んでいます。
先に予定されていたBBL(モーリス・ベジャール・バレエ団)の日本公演がコロナ禍で延期になり、今回のツアーは、全国の皆さんにベジャール作品を観ていただく貴重な機会となります。ベジャールさんが亡くなってもう14年。『ギリシャの踊り』は38年前の作品ながら、決して古めかしくなく、まるでつい最近に創られたかのような新しさがある。数あるベジャール作品の中でもとくに、爽やかで清々しい作品です。暗い話題の多い時期だけに、一人でも多くの方々にご覧いただいて、皆さんに明るい気持ちになっていただけたらと思っています。
取材・文:加藤智子(フリーライター)

──まずは20年間、お疲れさまでした。いまのお気持ちは?
奈良春夏 今は満ち足りた気持ちでいっぱいです。私には身にあまるような大役もたくさん踊らせていただき、思い残すことは何もありません。
──入団したのは溝下司朗芸術監督の時代でした。
奈良 もともと司朗先生の下で学びたいという思いがあって、東京バレエ団を目指していました。もちろん、多彩なレパートリーや海外ツアーでの活躍も知っていました。さらに、東京バレエ学校で指導していただいていた友田弘子先生(当時の東京バレエ団バレエ・ミストレス)、友田優子先生(同じく東京バレエ学校教師)に背中を押され、オーディションを受けました。
入団当初、司朗先生の下では飯田宗孝先生がバレエ・マスターとして活躍されていて、最初はとても怖い印象でした。が、2004年に芸術監督になられてからは、まるでお父さんのような存在に。普段はとても優しくて、私はそれに甘えていたかもしれません。もちろんバレエに関してはとても厳しかったですし、いつも的確なアドバイスをしてくださいました。
今振り返ると、想像にしていなかった大役を次々といただいたのは、まさに飯田先生が芸術監督の時代。たとえば、『ドン・キホーテ』のメルセデスやジプシーの若い娘、『眠れる森の美女』のカラボスなどは、もともとやりたいと思っていました。が、自分にはできないだろうなと思っていた役──たとえば『エチュード』のエトワール、べジャールさんの『舞楽』のソリスト、それからマラーホフ版『眠れる森の美女』のリラの精なんて、まさか私が!?と思っていたのだから。でも実は、カラボスのようなアクの強い役を学ぶことで、正反対のリラの精にも活かせる、こうした貴重な経験をさせていただき、本当にありがたく思っています。
──では、もっとも印象に残る作品、役柄は?
奈良 多すぎて、選ぶのは難しい! でも、まずはバレエ団初演(2009年)に携わったマカロワ版『ラ・バヤデール』のガムザッティと、"影の王国"の第2ヴァリエーションですね。初演ならではの苦労もありましたが、勉強になりました。
とくにガムザッティは、私がマカロワ版のことを大好きになった理由の一つ。その人物像は、王様の娘だから傲慢で、ちょっと意地悪な女性......というイメージではなく、一人の女性としてソロルを愛し、ニキヤとの三角関係に苦しむ女性でした。たとえば第3幕のヴァリエーションでは、そのことがはっきりと表現されます。テクニック面も体力的にも厳しい役柄でしたが、そういった表現で高めていけるストーリーがあります。
マカロワさんのリハーサルは、すごく集中して役柄に向き合うことができました。この経験で、演技面で大きく成長できたのではないかと思います。マカロワさんにいただいたメッセージ・カードは一生の宝物です。

──まずは18年間、お疲れさまでした!
岸本夏未 寂しい気持ちでいっぱいですが、長い間、大きな怪我も病気もなくつとめあげることができ、ほっとしています。最後の舞台は『ジゼル』。なじみ深い作品でしめくくることができて嬉しく思います。入団2年目から参加している作品ですので、思い入れがありました。子どもの頃、東京バレエ団の『ジゼル』のビデオを擦り切れるほど見ていたんですよ。(佐野)志織先生のドゥ・ウィリには本当に憧れました。
──『ジゼル』のコール・ド・バレエ初参加の思い出は?
岸本 先輩に注意され続けた記憶しかありません。前の先輩からも後ろの先輩からもチクチク注意されていました(笑)。最近はコール・ドの指導のお手伝いをさせてもらうようになりましたが、ここまで成長できたのは当時の先輩たちのおかげ。感謝しかありません。だから後輩たちには、「私もコール・ドで大変な思いをしてきたの!」って伝えたいです。
当時は注意を受けてばかりで、もう気分はどん底でしたが、憧れのバレエ団に入れたのだから、辞めたいとは思いませんでした。どうしても東京バレエ団で活躍したかった。絶対にソリストになりたい、あんな役、こんな役を演じたい!という思いで頑張りました。
──これまで取り組んだ中でもっとも印象に残る役柄、作品は?
岸本 一番に思い浮かぶのは、キリアンの『ドリーム・タイム』。当初、第3キャストでしたので東京の舞台では踊っていませんが、地方公演と海外公演の舞台で踊ることができました。身体の遣い方がクラシックとは全然違ううえに、ストーリーがない分、気持ちの持っていき方がとても難しい。そこを自分なりにストーリーを思い浮かべて取り組みました。あの素敵な衣裳、素晴らしい装置に照明──その空間に自分が立てるなんて、と本当に嬉しくなりました。その後、2019年の海外公演ではシングル・キャストに選んでもらい、ミラノ・スカラ座の舞台で踊ることができました。





東京バレエ団が6年ぶりに上演する名作「ジゼル」。今回初めて本作に取り組むダンサーも多く、稽古場では斎藤友佳理(東京バレエ団芸術監督)を中心に、連日熱いリハーサルが行われています。本日は作品の要ともいえる2幕のコール・ド・バレエ(群舞)を指導する佐野志織(東京バレエ団バレエミストレス)のインタビューをお送りします。

──東京バレエ団の『ジゼル』上演は6年ぶり。今回初めて『ジゼル』に取り組むダンサーが多いと聞きました。
佐野志織 そうですね。たとえば第2幕のコール・ド・バレエの女性たちは、半数ほどが初参加の若手です。が、彼女たちは『白鳥の湖』を何度も経験し、『ラ・バヤデール』も『ラ・シルフィード』にも取り組んでいますから、皆でどう合わせるか、呼吸をどう感じて踊るかということはよくわかっています。リハーサルで様々なインフォメーションを出すと、では自分たちはこうしようと自ら探究し始めますし、「先輩たちに見てもらう時間をとってもらっています」とも言っていました。頼もしく思います。
とはいえ、表現するものは作品によって異なります。『ラ・シルフィード』のコール・ドも妖精ですが、『ジゼル』の第2幕のウィリはまた全然違う。そこはしっかりリハーサルを重ねていきます。
──ウィリのイメージは、青く透明で、冷たい雰囲気が印象的ですね。
佐野 全体的なイメージはそうですが、今回、芸術監督の斎藤友佳理が『ジゼル』を指導するにあたって求めているもの、同時に、私自身もいろいろ学んで思ったのは、冷たさを強調するというより、そこに女性らしさというものが絶対に欠かせないということです。
私が東京バレエ団で初めて『ジゼル』に取り組んだのは、1996年の復活公演(15年の空白期間ののちに実現した)でしたが、その時の第2幕のコール・ドは、どちらかというと揃えることに重点が置かれ、フォーメーションは"真っ直ぐ"という印象。同時にウィリたちの冷たさが強調される形でもありました。けれど今回、ロシアの資料や映像にあたってみると、整列したウィリたちは"真っ直ぐ"ではなく、斜めに並んでいる。すると必然的に、肩の向きに角度がつき、より女性らしいラインが出てくるのです。
──では、第2幕のコール・ド・バレエの印象は、従来とは少し違ったものになりますか。
佐野 6年前の上演で初めてミストレスとして『ジゼル』に携わった際も、実は、この"真っ直ぐ"に少し抵抗を感じてはいたのです。
ウィリのイメージについて考えると、強くて冷酷で、男性を死ぬまで踊らせるという側面と、結婚前に亡くなった女性が、少女時代の、楽しく踊っていた頃のことが忘れられずに踊り続けているという側面があると思います。だとすると、ウィリたちには女性らしさが絶対に必要で、ただただ男性たちを殺す冷酷な存在であるというのとは違う形になってくるのではないかと。ですから、今度の舞台をご覧いただいて、従来と少し印象が変わったと感じられるかもしれません。
──だからこそ、女性らしいラインを求められているというわけですね。
佐野 ほかにもたとえば、身体を前に傾けて胸の前で両手を重ねる独特のポーズがありますが、あの両手は、自分の純血を守る、胸を隠すという意味があると考えられます。こうした細かい部分も、ちょっとした角度の違いで印象は大きく変わります。
斜めのフォーメーションにすることで、一人ひとりの姿は今まで以上に目立って見えることになるけれど、全員がきれいな佇まいでいられたらとても美しいものになるのではないかなと思っています。音楽の取り方についても今まで以上に敏感になるように、と指導しています。
──第1幕も踊りの場面がふんだんにありますね。
佐野 ペザントの踊り、ジゼルの友人たちのパ・ド・シスなどもありますね。皆で揃えて踊るところは揃えるけれど、それは2幕のウィリたちが整然と揃うのとは全く違う。もっと個人個人が見えて、ざわざわとしている。だって、世の中で皆と全く同じ動きをしている人なんて誰一人いないでしょう(笑)?
冒頭のヒラリオン登場の場面から、山あいの村にすむ人間の営みと、その中で自然に湧いてくる人間の感情が描かれていますね。収穫祭の賑わいも、そこに生きる一人ひとりの生活が見えてくるほどに、生き生きしていることが重要です。そうであればこそ、その後の場面がよりドラマティックに見えてくるもの。
1幕の終盤では、もちろん、そこで何が起きるかは予めわかってはいるけれど、いままさにそこで起きていることとして捉え、反応できる感性を持っていてほしいと思っています。
第1幕の見せ場の1つ、男女8名による華やかなペザントの踊り(パ・ド・ユイット)
──復活公演から25年。当時と今とでは、ダンサーたちの取り組み方に違いはありますか。
佐野 踊りに対する本質的な部分、作品への取り組み方は、当時も今も大きく変わっていないと思います。さらに、今のダンサーたちには様々な作品の経験があり、そこで得られた柔軟性がある。新制作で取り組んだ『くるみ割り人形』(2019年12月初演)でも、決められたことをこなすのではなく、自分たちでどう感じ、どう演じるかということを追求しました。そうした経験は『ジゼル』でも活きてくるのではないでしょうか。
──ではあらためて、バレエ『ジゼル』の魅力について、教えてください。
佐野 個人的な話になりますが、高校時代、発表会で初めて男性と組んで主役を演じたのが『ジゼル』でした。第2幕、それも後半のみでしたが、この時、物語の中で何者かになって踊るということを初めて経験し、それまでに味わったことのない感動を覚えたのです。それが転機となってあらためてプロを目指すようになったのですが、その後東京バレエ団で『ジゼル』の全幕に取り組むことができて、本当に嬉しく思ったものです。
『ジゼル』に携わっていると、人を愛するってどういうことなんだろう、と考えさせられます。2幕でジゼルは自分を裏切ったアルブレヒトを赦します。もしかしたら、ジゼルには"赦そう"という思いすらなく、ただ自分の愛を貫き、彼の苦しむ姿を見たくない、幸せになってもらいたいという一心で、ウィリたちから彼を守り、「彼を殺さないで」とミルタに懇願するのかもしれない。そんなところに、人は心の深み、愛を感じて涙するのだと思います。
取材・文:加藤智子(フリーライター)




 こちらは千秋楽で大トリをつとめた柄本弾と伝田陽美。そして友人役の二瓶加奈子とガマーシュ役の岡崎隼也。ちなみに、この4名は2008年入団の同期なのです!
こちらは千秋楽で大トリをつとめた柄本弾と伝田陽美。そして友人役の二瓶加奈子とガマーシュ役の岡崎隼也。ちなみに、この4名は2008年入団の同期なのです!




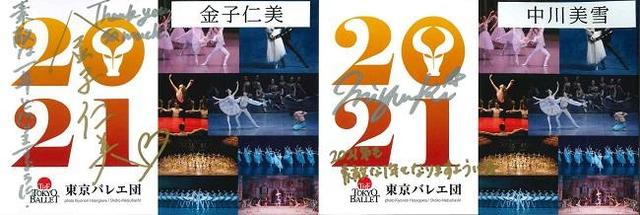



ただいま東京バレエ団は関内ホールにて、子どものためのバレエ『ドン・キホーテの夢』を上演中!
この公演は横浜市教育委員会が主催するもので、「心の教育 バレエの世界」をテーマに、横浜市立小学校の4年生を対象にした芸術鑑賞プログラムです。
今年はコロナ禍のために座席の間隔をあけ、客席は全員マスク着用のうえでの実施と、様々な対策を講じて上演しています。
さらに、子どものためのバレエ名物のカーテンコールや客席を使用した演出のとりやめなど、昨年とは違う形での開催となりましたが、会場は事前に配布されたプログラムに熱心に目をとおし、食い入るようにして舞台をみつめる小学生の熱気であふれています。
今回の公演では多数のダンサーたちが初役デビューを飾っています。

こちらは写真左から生方隆之介(バジル)、涌田美紀(キトリ)、見事主役の重責を果たしました。そして

長谷川琴音(写真左)、瓜生遥花(写真右)はキトリの友人役デビューでした。
このあとの公演の舞台裏は、公式Twitter, Instagramでご紹介してまいります。どうぞお楽しみに!
東京バレエ団「M」の10年ぶりの再演まであと9日! 今回の上演にあたり、初演時の「女」役誕生に貢献し、ベジャールとともに作品を創り上げてきた吉岡美佳(元プリンシパル・現東京バレエ団特別団員)が来団し、指導にあたっています。
後輩たちを厳しくもあたたく見守る吉岡に、現在のリハーサルの状況について話を聞きました。ぜひご一読ください。

──『M』では、初演時から「女」役を務められていました。
吉岡 ダンサーにとって、そのキャリアの転機になるような作品というものがありますよね。
東京バレエ団に入団後、数年の間に、ベジャールさんの作品では『ザ・カブキ』の顔世御前、『ドン・ジョヴァンニ』のヴァリエーションを踊っていましたが、その時点ではベジャールさんに直に指導していただくことがなくて、1993年の『M』がベジャールさんと直接一緒にお仕事をさせていただく初めての機会となりました。この時、ベジャールさんと一対一でリハーサルをさせてもらったことで、自分の中でちょっと何かが変わるものがあったと思います。たとえば、イリ・キリアンさんとのお仕事(『パーフェクト・コンセプション』世界初演)が実現したのはその翌年のことでした。
──ベジャールさんとのリハーサルでは、最初はとても緊張されたそうですね。
吉岡 そう、怖かったのです(笑)。あのブルーの眼で見つめられると、考えていることをすべて見透かされているような感じがして。でも実はすごく優しくて、会うといつも手にキスをしてくれて! 当時はまだ60代でしたから、ご自分で実際に動いて見せてくださることも。それを見て感じた通りに動いて見せると、「そうだね」「いや、もっとこういう感じで」と指示をいただく──。そうして稽古を進めていきました。それはダンサーとして本当に大きな経験でしたね。
──「女」という役づくりについては?
吉岡 ベジャールさんから「こういう役だからこう踊って」という説明は特にありませんでした。プログラムか何かの解説を見て知ったのですが、正式には「生命と再生の源を象徴する女」という役名です。
『M』には三島由紀夫のさまざまな作品のイメージが登場しますが、配役表には「禁色」とか「鹿鳴館」とか、場面のタイトルが書いてあって、私が演じた「女」の登場する場面は「鏡子の家」と記されていました。それで初めて三島の本を読んでみたのです。だからといって、あの「女」が「鏡子の家」のあの女性なのかというと、それはちょっと違うような気もします。でも、読んでいるのと読んでいないのとでは、舞台に立ったときに自分が発するもの、存在感、深みといったものが変わってくるはずです。
──強くて美しい女性、という印象です。
吉岡 ベジャールさんの作品ではよく、色でいえば白と黒という対照的な女性が登場します。『バレエ・フォー・ライフ』や『ブレルとバルバラ』もそうですね。白い衣裳の女性は、母親のような穏やかな愛。もういっぽうの黒い衣裳の女性は、もっと強くて激しい愛で、緊張感がある。『M』もまさにそう。白い衣裳の「海上の月」は母を思わせる慈愛に満ちた女性ですが、黒い衣裳の「女」は正反対。登場の場面では三島の分身の一人、IV
- シ(死)にからまれて、どこか死に対する予感とか怯えが見え隠れする。そこから男性(I - イチ)とのパ・ド・ドゥが始まりますが、決して穏やかな雰囲気ではなく、男性のお腹にぶつかっていく瞬間もある。私の中では闘牛のイメージでした。リハーサルの時にはつい躊躇してしまったけれど(笑)。

2005年の公演より。女役を演じる吉岡美佳
──今、リハーサルではどんなことに配慮して指導されていますか。
吉岡 ベジャールさんの振付は実にシンプル。言われた通りの振付をきちんとその通りに踊ることで、その振付が生きて、作品の中のその場が生きてくるものだと思います。ダンサーたちには、ベジャール作品を大事に踊ってほしいなと思います。そうでなければ、いまこうして取り組む必要などないわけですから。
──10年ぶりの上演となる今回は、ほぼすべての役柄が新キャストに。フレッシュな『M』となりますね。
吉岡 演じるダンサーが変われば、作品は全く違うものになるもの。でも少なくとも、私も、(初演ダンサーで、今回ともに指導にあたっている)小林十市さんも、高岸直樹さんも、当時ベジャールさんに言われたこと、教えていただいたことを、最大限、ダンサーたちに伝えようと努めています。それは私たちの使命だと思うし、やりがいがあります。ベジャール作品は、映像を見て振付を覚えるだけで上演できるものではないし、東京バレエ団のオリジナル作品を途絶えさせるわけにはいかない。こうやって作品を継承していくことはとても大切なことと考えています。初演後のヨーロッパ・ツアーで高い評価を受けた作品ですが、いまあらためて、日本のお客さまに観ていただきたいと思っています。

ボリショイ劇場の前で。柄本弾、秋山瑛、宮川新大審査員を務め...
今週金曜日から後半の公演が始まる「ロミオとジュリエット」は、...
新緑がまぶしい連休明け、東京バレエ団では5月24日から開演す...
あと1週間ほどで、創立60周年記念シリーズの第二弾、新制作『...
2023年10月20日(金)〜22日(日)、ついに世界初演を...
全幕世界初演までいよいよ2週間を切った「かぐや姫」。10月...
バレエ好きにとっての夏の風物詩。今年も8月21日(月)〜27...
見どころが凝縮され、子どもたちが楽しめるバレエ作品として人気...
7月9日、ハンブルク・バレエ団による、第48回〈ニジンスキー...
7月22日最終公演のカーテンコール オ...